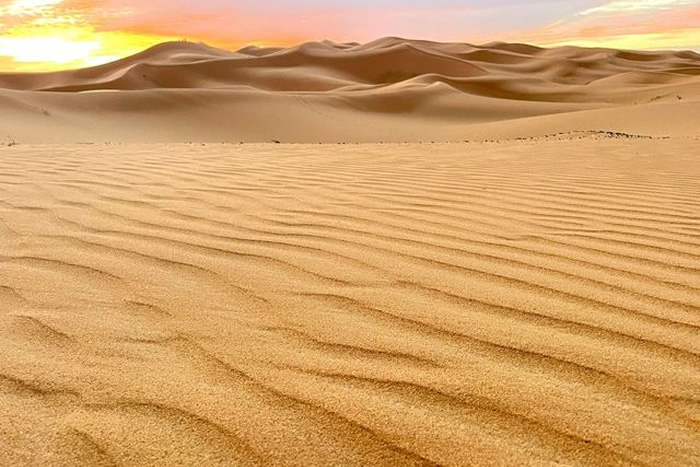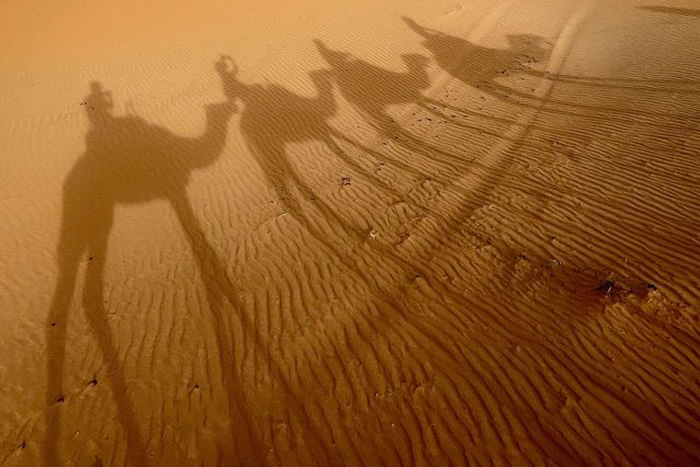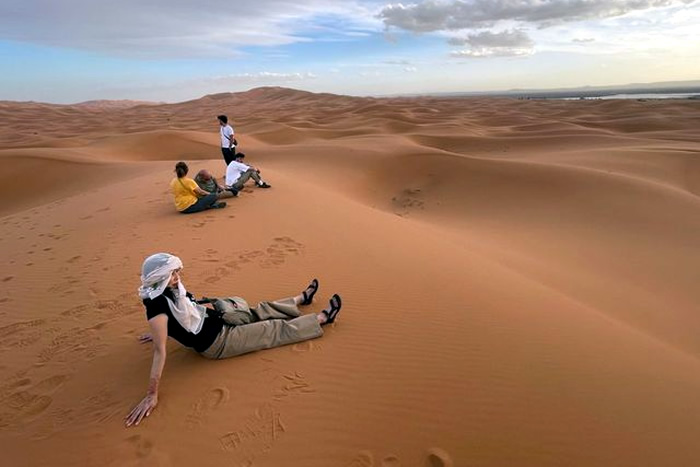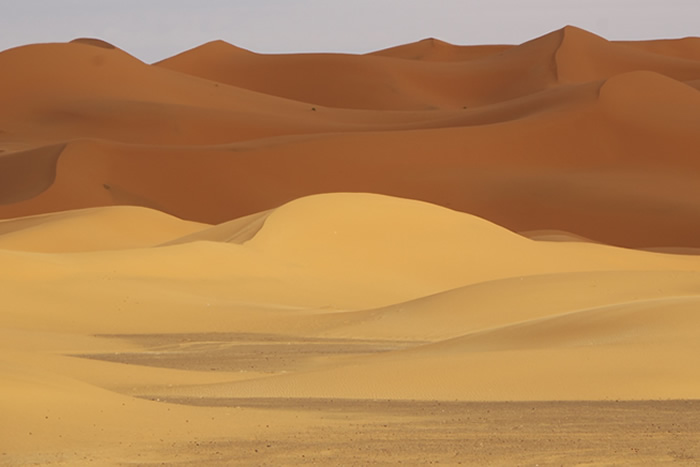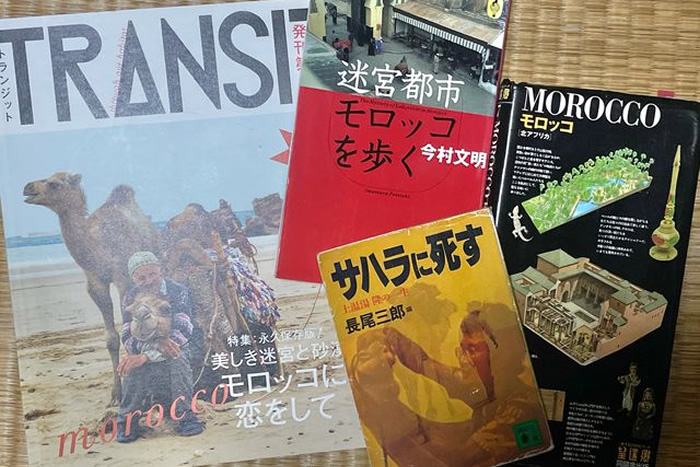人口・面積が大きいことはもちろんですが、その文化の多様性から一つの「世界」ともいえる大国、インド。歴史・文化・言葉などが国内で多様に異なっていますが、大きくは北と南の2つに分かれます。南インドでは、中世以降西から侵入してきたイスラームの影響を大きく受けてきた北インドと異なり、インド固有の宗教であるヒンドゥー教国家が存続している期間が長く、独自の歴史を歩んできました。南インドに属するカルナータカ州にも、様々な時代の国々が築いてきたヒンドゥー寺院がよく残っており、そのどれもが非常にレベルの高い精巧な石彫を刻んでおり、初めて見れば「すごい」の一言に尽きるものばかりです。
そんなカルナータカの石彫美術を見て回る「デカンの至宝 幻の王都ハンピと石彫美術探求の旅」を今回は2回にわたってご紹介します。

チェンナ・ケーシャヴァ寺院「鏡を見る美女」
ツアーはカルナータカ州の入口となる人口1,000万人の大都市、バンガロールからスタートです。初日はバンガロールに宿泊し、翌日、まずは西に180km行ったところにあるハッサンの町へ向かいます。途中、”Café Coffee Day”で一服。国内に1700店以上の店舗を持つ巨大チェーン店ですが、カルナータカ州の発祥です。インドというと、チャイを一日中飲んでいるイメージがありますが、カルナータカ州はコーヒーで有名で、全インドのコーヒー生産量の約70%を占めているそうです。
ハッサンの町付近には、ホイサラ朝 (1026-1343) という王朝が存在していました。ホイサラ朝は南インドの建築発展史上重要な一時代を築いた王朝で、ホイサラ様式と呼ばれるヒンドゥー寺院建築の様式が確立されています。

ホイサラ朝の名の由来で紋章にもなっている、ライオンを倒すサラ少年の像
ヒンドゥー教では神の像を作って崇拝するので、ヒンドゥー寺院は神が宿ることになる像を安置する部屋を設置します。これを聖室 (ガルバグリハ) と呼びます。その前面に、神をもてなし礼拝するマンダパ (拝堂) があり、この <聖室+マンダパ> というのがヒンドゥ寺院の基本形となります。この単純な形を発展させて荘厳にしようとすると、聖室は窓のない厚い壁で囲まれた正方形の部屋でこれ自体が巨大化することはないので、その周囲に礼拝のための繞道を巡らせて平面を広げたり、聖室の上部には高く塔状に石を積んだり、聖室を広い列柱ホールとしたりします。ホイサラ様式では、聖室の上の塔は高くないですが、平面的に、正方形を少しずつ回転させて形成したような星型の形状を持っているのが外観的にきらびやかに見せる形となっています。さらに側面には寸分の隙間もないほどに神話場面や動植物紋様の浮彫がうずめいており、圧倒されること間違いなしです。
ハッサン近郊の有名寺院2つを訪れました。ひとつは、ホイサラ朝初期の首都であったベルールの町にあるチェンナケーシャヴァ寺院。「チェンナ」とは「美しい」、「ケーシャヴァ」はヒンドゥー教「ヴィシュヌ神」を意味します。名前の通り、八百万ならぬ3,300万とも言われるインドの神々の中でもシヴァ神と双璧の人気を誇るヴィシュヌ神を祀っています。32角の星型の基盤の上に本殿が建っています。神々だけでなく人間の女性像なども、側面だけでなく内部の壁や柱も飾っており、とにかく派手です。

南インドの寺院建築の特徴の一つであるゴープラム (塔門)
|
|

ヴィシュヌ神の乗り物であるガルーダ
|
次いで、ベルールから30分ほどのところにある、ハレビードの町へ。ベルールの後にホイサラ朝の都が置かれた場所です。ここにあるホイサレーシュワラ寺院を訪れました。チェンナケーシャヴァ寺院を建立したのと同じヴィシュヌヴァルダナ王という王が、自分と王妃の為に建立した寺院で、王の為の神殿と王妃の為の神殿が2連になってつながっている珍しい造りの寺院です。このお寺の主神は、シヴァ神。世界を維持するヴィシュヌ神に対して、シヴァ神は破壊神とされています。ヴィシュヌ神やシヴァ神にはそれぞれ乗り物があり、シヴァ神の乗り物はナンディという牛で、これがヒンドゥー教徒が牛を神聖視する理由になっています。そのためこの寺院では、王と王妃のそれぞれの神殿の前に、ナンディ像が置かれたお堂が設置されるという構造になっています。同じく星型の基壇と本殿が構造的に派手な形状をしていますが、驚かされるのはチェンナケーシャヴァ寺院に増して徹底的に彫り込まれた、側面の石彫の数々。何も彫刻のない「ただの壁」である部分を見つけ出すのが困難なほどで、「彫刻の洪水」「平面恐怖症」といった形容詞がしっくりきます。

文字通り隙間なく彫刻で覆われた壁面
|
|

マンダパの前のお堂に鎮座するシヴァ神の乗り物、ナンディ
|
ガイドさんのご両親がホイサレーシュワラ寺院の脇でチャイ屋さんを営んでおり、チャイをごちそうになりました。冬でも30度を超える南インドの熱気ですが、コーヒーで有名なカルナータカと言っても、インドと言えばやはり熱々のチャイに限ります。
翌日、ハッサンから320km北方にあるホスペットの町へ、インドの田舎の風景の中、一日かけて移動しました。今度は、ホイサラ朝から時代を遡った、前期チャールキヤ朝 (534頃-753) の時代を中心とした遺跡を訪れていきます。まずはホスペットからさらに120km北西にあるアイホーレの遺跡に向かいました。
アイホーレは今では小さな村ですが、ヒンドゥー寺院建築の発展史上重要な寺院群が存在しています。ここにはドゥルガー寺院という寺院があり、他では見ることのない後円の縦長な形 (馬蹄型) をした珍しい形状をしています。ドゥルガーというとヒンドゥー教ではシヴァ神の妃パールヴァティの憤怒形の戦いの女神が有名ですが、この寺院の名前は女神に由来するものではありません。「要塞」という意味だそうで、実際に寺院の近くに城壁が存在しています。馬蹄形を縁取るように回廊が巡っており、その回廊にヒンドゥー神話を表現した見事な彫刻が施されています。すぐそばにあるラド・カーン寺院は、正方形の形をした本殿に玄関をつけ、緩い傾斜の屋根を載せた、ドゥルガー寺院とは全く異なる形をしているのが面白いです。古代インドでは今よりも木材が豊富で、寺院も木造が主流だったそうですが、やがて岩山に穴をうがつ石窟寺院や、石造寺院に変わっていったという流れがあります。古代に建てられた木造寺院は残っていませんが、このラド・カーン寺院は木造寺院の外観を石造で模して作ってあります。

馬蹄形をしたドゥルガー寺院
|
|

ラド・カーン寺院。屋根上の丸太上の棒は寺院が木造だった頃の形状を模していると言われます
|
アイホーレの次は、パッタダカルという遺跡を訪れました。ここは前期チャールキヤ朝の王が戴冠の儀式を行なった町でした。ヒンドゥー寺院の様式は、北方と南方で分かれて大きく異なりますが、ここパッタダカルの7-8世紀に建てられた9つの寺院群では、その両方の様式が混在しているという珍しい場所であることが評価され、ユネスコの世界遺産に登録されています。

パッタダカル寺院群
北方型と南方型の違いを端的に示すのは、聖室の上に立ち上がる塔状部のデザインです。北方型では塔状部が上部に向けて段々と細くなる砲弾状をなして高く伸び上がり、これをシカラと呼んでいます。これに対して南方型の塔では、小さな祠堂群が横に並んで層をつくり、この水平層が階段状に積み重なってピラミッド型の塔状部を形成しています。
パッタダカルの寺院群の中の代表とも言えるのが、ヴィルパクシャ寺院。前期チャールキヤ朝が隣のタミルナドゥ州にあったパッラヴァ朝に勝利した記念に建てられました。パッラヴァ朝の首都カーンチープラムは南インドを代表する寺院のある場所で、その影響を受けて典型的な南インドの様式になっています。北方型と南方型が混在しているというのは、当時のチャールキヤ朝の王がこのように他地方から職人を集めていたことを意味しています。

ヴィルパクシャ寺院 (南方型)
|
|

ガラガナータ寺院 (北方型)
|
後編では、バーダミにある石窟寺院からご紹介します。
参考文献:
『南アジアを知る事典』 平凡社
『インド建築案内』 TOTO出版
『ユネスコ世界遺産⑤』 講談社
『インドの大遺跡』 講談社






























 名峰ハンテングリ(7,010m)南イニルチェク氷河キャンプより
名峰ハンテングリ(7,010m)南イニルチェク氷河キャンプより