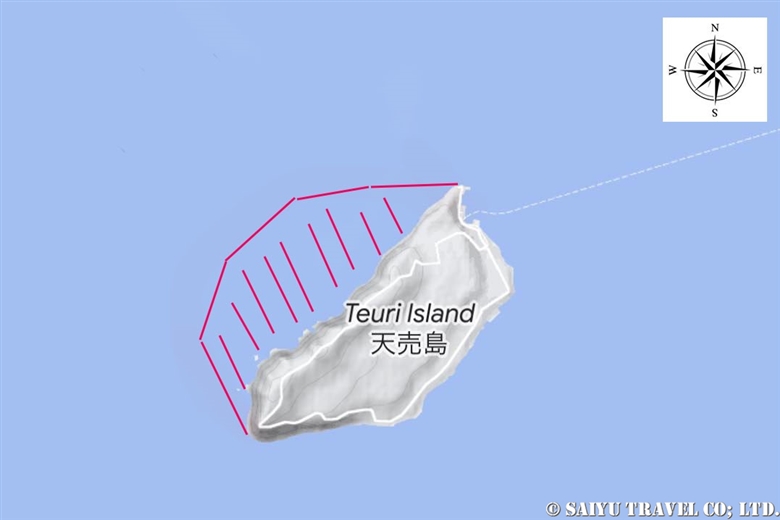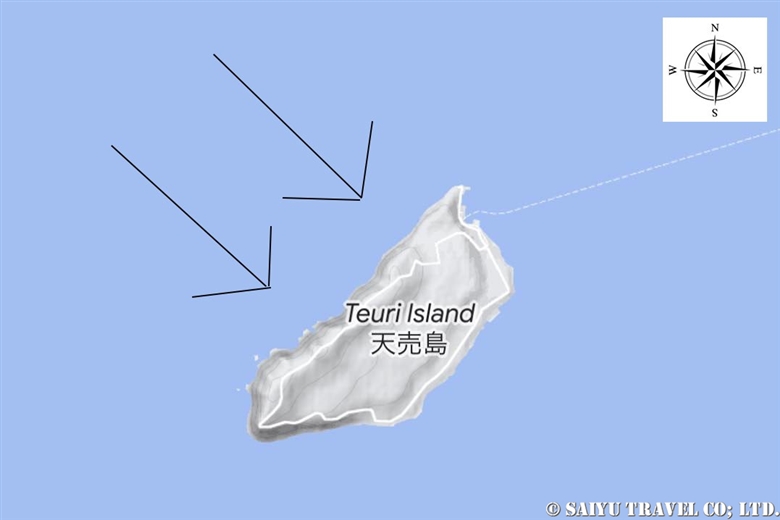世界最大の両生類・オオサンショウウオ
岐阜県飛騨と美濃の中間にある山里を流れる和良川には、日本固有種で、国の特別天然記念物でもあるオオサンショウウオが多く生息しています。また、6月中旬になると、和良川の支流ではたくさんのホタルを鑑賞することができます。
観察時の注意事項として、オオサンショウウオに触れることは一切出来ません。何故ならオオサンショウウオは、日本の特別天然記念物であり絶滅危惧種Ⅱ類(VU)(環境省レッドリスト)に指定された天然記念動物として手厚く保護されている生き物だからです。そのため、皆さんは観察しか出来ませんが、水中マスク越しに写真や動画撮影をしていただけます。

石の中に隠れるオオサンショウウオ
オオサンショウウオは夏場は数分おきに水面に顔を出して呼吸をします。生息場所から水面まで上がり、鼻を水面に出して呼吸し、元の位置に戻るので、泳ぎが苦手のオオサンショウウオが必死に元の位置に戻る姿は、母性本能をくすぐられるような可愛さがあります。

オオサンショウウオの正面顔

河原をのそのそと歩く
観察をする日中、夜行性のオオサンショウウオは頭を石の中に入れて隠れています。明るい場所が嫌いなのですが、呼吸をする時は顔を水面に出しやすい場所に移動しますので、後ろ向きのオオサンショウウオでもじっと待っていれば正面顔をしっかり撮影できます。粘りと根性があれば、スーパーショツトを撮影していただけるでしょう。また、観察できると一番嬉しいのがおおあくびです。オオサンショウウオが口を全開させるこのシーンはなかなかタイミングが難しいですが、捉えることが出来れば最高です。このほかにも魚を捕食したり、脱皮をする様子など、オオサンショウウオの様々な仕草を楽しむことができます。
オオサンショウウオは時には川から上がり、堰堤の上などに上陸してくれることも年に数回あります。こんな場面に遭遇した方は超ラッキーです。この和良川の地区では広い範囲に数多くオオサンショウウオの生息が確認されていますが、2025年1月現在でも中国オオサンショウウオとの交雑個体は発見されておらず、日本固有の純血のオオサンショウウオのみが生息しています。

カワヨシノボリ

日本固有種のニホンイシガメ
オオサンショウウオのほかにも、川辺に生息する生き物たちも紹介しています。和良川に生息する鮎は、今では「和良鮎」と呼ばれるブランド鮎に変貌しました。和良鮎の最大の魅力は、なんといっても香りです。涼しげなスイカのような香りで、その香気で夏の河原一帯を満たしてしまうほどです。良質な藻類をいっぱいに詰め込んだ腹ワタは、食べた瞬間にその香りが口の中いっぱいに広がり、ほろ苦さの中に甘さと旨味もある絶妙な風味があります。

古民家 「七福山」
宿泊は築170年の古民家。囲炉裏を囲みゆっくりおしゃべりしたり、お酒を酌み交わしたりと、日本の伝統を感じることができます。
食事は和食を中心に、川魚、山菜など季節の素材を活かした料理が提供されます。山家ならではの静かな空間は、行きかう旅人の癒しの場。ここを切り盛りする女将さんも話好きなので、ツアーに参加した際にはぜひ女将さんとお話を楽しんでいただきたいです。
Text & Photo : Yoshihiro ITO
★関連ツアー:水中写真家・伊藤義弘さん同行 和良川のオオサンショウウオとホタルの乱舞
水中写真家、ダイビングインストラクター。西表島での体験ダイビングで海に目覚め、インストラクターの資格を取得。世界各地の海と川を潜る中で、豊かな生態系を有するふるさと岐阜県の川に魅了される。誰もやっていない分野のガイドになる決意をし「伊藤潜水企画」を設立。川に住む生きものをテーマに、川の生きもの案内人として観察会等を企画運営。