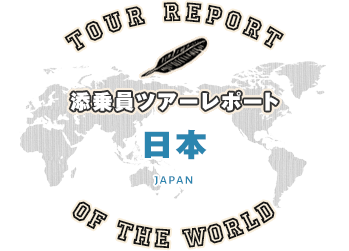花の尾瀬フラワートレッキングとチャツボミゴケの群生地を歩く~トレッキング1日目~
- 日本
2021.06.17 update
夏がくれば思い出す はるかな尾瀬 遠い空
霧のなかにうかびくる やさしい影 野の小径
水芭蕉の花が咲いている 夢見て咲いている水のほとり
石楠花色にたそがれる はるかな尾瀬 遠い空
~童謡・唱歌「夏の思い出」より
大阪支社の高橋です。
私自身が高山植物に興味を持ち始めたのは、西遊旅行に入社する以前のスイス添乗がきっかけでしたが、その後、日本各地の景勝地へ訪れた際にも素晴らしい花々に出会い、さらに深く知りたいと感じ、今に至ります。
日本各地で高山植物の花々が美しい場所はたくさんありますが、美しい花々との出会いに衝撃を受けた場所の1つが「尾瀬」でした。そんな思い出深い尾瀬の地で再びゆっくりと花の観察を楽しみたいという想いから、今回の「完成:花の尾瀬フラワートレッキングとチャツボミゴケの群生地を歩く」のツアーを造成させていただきました。
今回は、童謡・唱歌「夏の思い出」にも歌われる尾瀬の情景に思いを馳せながら、尾瀬の花の観察を楽しみ、尾瀬ヶ原から尾瀬沼を目指す「花の尾瀬フラワートレッキングとチャツボミゴケの群生地を歩く」をご紹介します。
山小屋に泊まりながらのゆったりとしたトレッキングのため、花の観察が大好きな方はもちろん、朝夕の尾瀬の撮影を楽しみたい方にもオススメです。

ニッコウキスゲが咲く尾瀬ヶ原(7月)
尾瀬国立公園
尾瀬が植物の宝庫として知れ渡るようになったのは、1898年(明治31年)に植物学者・早田文蔵氏が調査し、植物の宝庫として尾瀬と会津駒ケ岳を紹介したことに始まり、1905年には登山家で植物学者でもある武田久吉氏が尾瀬の紀行を発表して広く世間に知れ渡るようになりました。
尾瀬国立公園は、2007年(平成19年)に日光国立公園から分割、会津駒ケ岳、田代山などを新たに編入し、福島県、栃木県、群馬県、新潟県の4県に跨る、29番目の国立公園として誕生しました。
それ以前には、1960年(昭和35年)に国の特別天然記念物に指定され、自然生態系の価値が評価されて2005年(平成17年)にラムサール条約湿地に登録されました。
通常、鳩待峠~尾瀬ヶ原・見晴~尾瀬沼~大清水と縦走するトレッキングは1泊2日プランで紹介されることが多い中、ツアーでは、3つの理由で2泊3日プランとしています。
■ 時間に追われず尾瀬の風景や花の観察を楽しむため
■ 観光客の少ない朝夕の風景の見学、撮影を楽しむため
■ 1日の歩行時間・距離を短くし、体力的な不安を軽減するため
少々前置きが長くなりましたが、ツアーのハイライトである「尾瀬フラワートレッキング」を順を追ってご紹介します。
尾瀬フラワートレッキング1日目(9㎞/約4時間)
フラワートレッキング1日目は、本州の分水嶺にあたる鳩待峠(標高1591m)よりスタートし、尾瀬の代名詞ともいえる風景が広がる尾瀬ヶ原(標高1400m)を目指します。
ガイドブックなどでは、鳩待峠から尾瀬ヶ原・見晴までは「9km/3時間」と表記されていますが、ツアーでは花の観察を十分に楽しみながらゆっくりと歩くため、4時間とさせていただいています。
1.鳩待峠(1591m)~山の鼻(1400m)
群馬県側の主要登山口である鳩待峠(1591m)より、標高差191mの下りルートからスタートします。ここは膝に負担を掛けず、慎重に歩くように心がけますので、ご安心を。
ブナの樹林帯に咲く花の観察や鳥のさえずりなどを聞きながら、ゆっくりと下ります。
天気が良ければ、木々の間から至仏山(標高2228m)も展望できるかもしれません。
スタートして30~40分ほど歩くと、ヨセ沢を渡り、そこを過ぎると左手に川上川が見え始めます。川上川の畔まで歩くと、木道は平坦となり、フラワートレッキング1日目における最大の注意ポイントはクリアです。

ミズバショウの花が咲いている尾瀬(5月下旬~6月上旬)
川上川の流れを左側に感じながら、途中でテンマ沢を通過しますが、このあたりがミズバショウの群生地として有名なポイントです。
ツアーは6月末、7月に設定しているため、ミズバショウのシーズンは終わっていますが、通過するだけでなく、時季外れのミズバショウが残っていないか、探してみましょう。
その後、カラマツやミズナラの林を抜けて、川上川に架かる橋を渡ると、山の鼻(標高1400m)に到着です。山の鼻には、1周2kmの植物研究見本園があり、開花情報を伺いつつ、是非ともこちらも巡りたいと考えています。

コバイケイソウ(6月末~7月上旬)
2.尾瀬ヶ原(標高1400m:山の鼻~竜宮~見晴)
山の鼻から、いよいよ尾瀬を代表する風景である尾瀬ヶ原へ入ります。
約35万年前、燧ケ岳の火山活動による溶岩流や土石流によって形成された堰止湖が長い年月を経て、湿原化したとされています(形成過程は複雑で一様ではありません)。
東西約6km、南北約2.5km、約650haに及ぶ本州最大の湿原は、川の流れや畔に生い茂る拠水林(きょすいりん:湿原を分断する帯状の樹林帯)により、3つに区分されます。
■ 山の鼻~牛首のエリア:上田代(かみたしろ)
■ 牛首~竜宮のエリア :中田代(なかたしろ)
■ 竜宮~見晴のエリア :下田代(しもたしろ)
尾瀬ヶ原では、上田代→中田代→下田代と順に歩き、移り変わる景色や尾瀬の花々を楽しみながら、平坦な木道をゆっくりと歩きます。

カキツバタの咲く尾瀬ヶ原(6月)
尾瀬ヶ原の泥炭層には高木が育つほどの栄養分はありませんが、尾瀬ヶ原に流れる川沿いには山から豊富な栄養分を含んだ土砂が流れ、運ばれてくるため、樹木が育つ環境ができ、拠水林を形成します。山の鼻より少し歩いた上田代エリアや、中田代エリアから下田代へ差し掛かる竜宮周辺で拠水林が観察できますので、注目です。
尾瀬ヶ原には、大小1800もの池塘(ちとう)と呼ばれる池(水たまり)があり、湿原が発達するなかで凹地に水がたまり池となったもので、尾瀬を代表する風景の1つです。天気が良ければ、池塘に周囲の山々を映しだし、上田代エリアでは燧ケ岳を映した「逆さ燧」もご覧いただけるポイントもあります。

池塘に燧ケ岳が映り込む
また、7月ツアーでは、池塘に咲くオゼコウホネやヒツジグサなどの水生植物も観察できるかもしれません。

ヒツジグサ(7月上旬~)
中田代エリアでの見どころの1つが「竜宮現象」です。
竜宮現象とは、湿原を流れる水が地中に吸い込まれ(伏流口)、別のポイントから湧き出す(湧出口)現象をいい、竜宮十字路の手前でご覧いただけます。
竜宮十字路を通過し、尾瀬沼から流れる沼尻川を渡ります。
この沼尻川は中田代エリアと下田代エリアの境界線であり、群馬県と福島県の県境でもあります。トレッキング1日目は「県跨ぎトレッキング」でもあります。
東北地方の最高峰・燧ケ岳(標高2356m)が間近に迫る下田代エリアでは、花々の観察を楽しみながら、平坦な木道を歩き、フラワートレッキング1日目の宿泊地である見晴「桧枝岐小屋」を目指します。

尾瀬ヶ原から至仏山を望みながら歩く
ツアーでは、お弁当を持参せず、宿泊の山小屋に到着してから昼食を召し上がっていただく予定です。
昼食後は、基本自由にお過ごしいただきます。ご希望の方は、山小屋周辺の花の観察やヨッピ吊橋方面のハイキングへご案内します。
周辺で散策を楽しむも良し、撮影に励むのも良し、のんびりコーヒーでも飲みながら周囲の風景に溶け込むのも良し。天気が良ければ、夕食前に夕焼けに染まる尾瀬ヶ原の風景を楽しむことができ、至福の時間をお過ごしいただけます。

カキラン(7月)

ツルコケモモ(6月中旬~7月上旬)
尾瀬では6月中頃から山々の雪が溶け、湿原に色とりどりの高山植物が一斉に咲き始め、6月下旬に高山植物の最盛期を迎え、7月中旬頃から夏の尾瀬を代表するニッコウキスゲが咲きそろいます。
初めての山小屋泊トレッキングでも安心してご参加いただける日程となっておりますので、是非ご検討ください。
※7月17日出発コースは、大清水からスタートし、尾瀬沼、尾瀬ヶ原を抜け、鳩待峠を目指す逆回りコースとなります。
次回は、フラワートレッキング2日目(尾瀬ヶ原~尾瀬沼)をご紹介します。