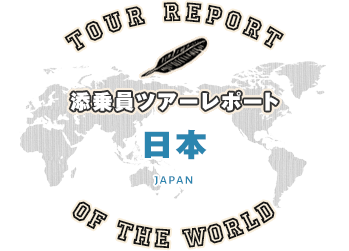春の九州スペシャル
花咲く九重連山から名峰6座に登り桜島へ
- 日本
2021.03.04 update
九州には百名山が6座あり、その内、屋久島の宮之浦岳を除く5座と200名山の名峰・高千穂峰に登る8日間の九州縦断ツアーをご紹介します。
※今回のレポートは2020年10月末の紅葉の時期、そして高千穂峰の登山を除いた7日間コースのものです。
1日目
大分空港にお集まりいただき早速、専用車にて九重山の登山口・大曲へ。大分空港を出発し、高速道路へ入り、一般道の通称「やまなみハイウェイ」へと入っていきます。九重町へ入り、その名の通り大きく曲がった道に駐車場があるだけの登山口・大曲ですが、紅葉やお花の名峰・三俣山を登るにはここからが便利。準備体操をして出発です。

登山口の一つ・長者原から三俣山

この日は昨日までの雨の影響が随所に
この日は九重特有の滑りやすい黒い土がぬかるみとなっており、いきなり靴が汚れてしまう洗礼。正面に硫黄山が噴気を上げているのが見えてきます。ガレ場の登りを行き、すがもり越に到着。一息入れて三俣山を目指し急登を行きます。まずは西峰(1,678m)へ。

三俣山へ笹の急登を行く

振り返ると明日向かう久住山、中岳方面が視界に
再度の登りで本峰(1,745m)に登頂です。本峰から北峰、南峰が見えます。西峰を加えて4つの頂があるのですが、3つの頂に見えるため三俣山の名が付きました。5月はシャクナゲ、6月はミヤマキリシマが美しいこの山ですが、今回は紅葉が出迎えてくれました。

真っ赤に染まる三俣山・北峰の紅葉
ツアーでは訪れませんが、これまた名峰の九重連山・東パート。平治岳や大船山もよく見えます。

平治岳(ひいじだけ1643m)

南峰(1,743m)と奥に大船山(たいせんざん1,787m)
その名の通り砂浜のような北千里ヶ浜へと下り、眼下に坊ガツルのテント場が見えてきます。山荘まで慎重に下山し、本日の宿、法華院温泉山荘に到着。標高1,303mにある九州最高所の秘湯を楽しんでいただけます。石鹸、シャンプーは使えませんが、山小屋で入るお風呂は格別です。

この日の夕食は鳥大根、豚しゃぶなどでした
2日目
山荘裏手から登りがスタート。昨日下ってきた道です。ガレ場を登ると広い北千里ヶ浜に出ます。昨日の分岐を左手に久住山、中岳といった九重連山の主脈、南パートへの登りが始まります。久住分かれの峠に出ると、牧ノ戸峠からの人が増え賑やかに。最高峰の中岳を目指します。中岳と御池は、古くから信仰の対象として崇められてきました。

御池の奥に九重連山の最高峰・中岳

時期によっては霧氷が見られることも
中岳に到着です。平治岳と大船山、そして眼下に坊ガツル。坊ガツルは長者原のタデ原湿原とともに、中間湿原として国内最大級の面積を有する湿原で「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」としてラムサール条約の登録湿地となっています。

九州本土最高峰・中岳(1,791m)

平治岳と坊ガツル湿原
次は久住山へ。分岐に戻り久住山へのザレ場の登り。久住山山頂はいつも大人気です。

久住山への登り

久住山(1,787m)山頂

翌々日登る祖母山が見えました
久住山避難小屋まで下山してお弁当タイム。翌日登る阿蘇山も見えています。牧ノ戸峠への下山路は広く整備されていて、たくさんのハイカーとすれ違いながら気持ちの良い道を下山。右手に見えていた星生山(ほっしょうざん:1,762m)の西斜面は見事な紅葉の色づきでした。

星生山の西斜面の紅葉
途中の沓掛山からは阿蘇山の阿蘇五岳がよく見えました。根子岳をお顔としたお釈迦様(涅槃像)に例えられます。

沓掛山(1,503m)から望む阿蘇五岳
牧ノ戸峠へと下山し、阿蘇山の麓の宿へ向かいます。
3日目
※このレポートでは阿蘇五岳の内、比較的易しい2座に登りましたが、火山ガスや天候による規制がない場合、最高峰の高岳、そして中岳を縦走します。

草千里ヶ浜から烏帽子岳
観光地の草千里ヶ浜から烏帽子岳、杵島岳、そして噴煙を上げる中岳と奥に最高峰の高岳がよく見えます。烏帽子岳の登山開始。天気が良く、カルデラの地形が良く理解出来ます。遠く、長崎の雲仙岳(普賢岳)も見えます。気持ちの良い尾根歩きからやがて登りへ。

階段の登り

シラヤマギク
少し切れ落ちた斜面にある階段を慎重に通過し山頂へ。

烏帽子岳山頂より祖母山を望む

烏帽子岳山頂からの九重連山
山頂からは360℃の展望で祖母山と九重連山もバッチリ見ることが出来ました。下山はダイレクトに草千里ヶ浜へ。

噴煙上がる中岳火口

正面には九重連山がどっしり
雄大な阿蘇中岳と高岳の景色、そして昨日登った九重連山を見ながら下山。次の杵島岳はアスファルト道がメインです。

杵島岳山頂から噴煙上がる中岳火口と中岳、奥に最高峰の高岳
下山後、南側からの阿蘇を眺めながら宮崎県に入り、宮崎県随一の名勝、高千穂峡を訪れました。

高千穂峡・真名井の滝

高千穂峡でボートを楽しむ人たち
高千穂峡は、阿蘇火山活動の噴出した火砕流が、五ヶ瀬川に沿って帯状に流れ出し、急激に冷却されたために柱状節理の懸崖となった峡谷です。遊歩道を往復1時間程歩き、眺めを楽しみます。
4日目
祖母山の高千穂側の登山口はバスは入れず、タクシーに乗り換えなければなりません。北谷登山口から出発です。杉林のジグザグ道を登っていき、開けた尾根の展望台に到着。澄んだ青空に阿蘇、九重、遠く由布岳も見ることが出来ます。

展望台から九重連山
祖母山は隆起した山で、これまでと少し違い、優しいブナ林のトレイル。緩やかなアップダウンの尾根道を行くと、宮崎・熊本・大分の三県境です。
開けた国観峠で大分県の神原(こうばる)コースと合流し、ここからは掘れた足元の悪い道を登り、山頂へ。360℃の展望が迎えてくれました。明日登る霧島連山も遠く見えています。

傾山(1,605m)が聳えます

祖母山(1,756m)山頂
傾山が大きく聳えます。主稜線を忠実に辿る縦走路は祖母山の九合目小屋から傾山の山頂近くの九折越小屋まで丸一日かかりますが、九州の名ルートです。来た道を下山し、一路鹿児島・霧島温泉へ。
5日目
湯けむりがもくもくと上がる霧島温泉の朝。バスで少し行くとすぐに宮崎県側に入り、登山口のえびの高原に到着です。アカマツの樹林帯へと入っていき、5合目に着くと展望が開け、大浪池が見えてきます。大浪池は、直径630m、周囲約2km、常時水を湛える火口湖としては日本で最も高い場所にあります。霧島連山の火山活動によって約4万年前に形成された火口の跡に水がたまって出来ました。

大浪池が見えてくる

韓国岳を見上げる
8合目からは左手に爆裂火口が見え、山頂まではもうすぐです。

8合目付近から見る爆裂火口

山頂へ最後の登り
山頂からは正に漢字の「山」の形の二百名山・高千穂峰(1,574m)と噴煙くすぶる新燃岳(1,395m)が良く見え、360℃の展望を存分に楽しむことが出来ます。

高千穂峰と手前に新燃岳
眼下に大浪池を見ながら縦走開始です。

火口湖がくっきり

韓国岳避難小屋
下り切った所に韓国岳避難小屋があります。一登りして大浪池の縁に到着。展望を楽しみながら半周します。どちらも同じくらいの距離ですが、今回は東回りコースを歩きます。

振り返ると韓国岳

見事なブルーの火口湖です
大浪池口に到着し、石畳の道を下山します。バスで薩摩半島の南端、指宿温泉へ。
6日目
開聞岳を目指して出発。展望の良いところで写真タイム。雲がいい感じです。

開聞岳全景
かいもん山麓ふれあい公園に到着。2合目から登山道です。
さすがに南国、そして標高の低さもあり、早々に汗が噴き出ます。シダ類やコケが広がる、常緑広葉樹の森の中を登っていき、時折セミの鳴き声が聞こえてくる山の中はまるで季節が夏に戻ったようでした。途中、ツチトリモチなど珍しい南方系の植生も見ながら進んでいきます。

南国の山ムードが漂います

大岩を越えて行く
登りの際の天候は少しかすんでおり、展望地から晴れていれば見られる種子島や屋久島は見ることは出来ませんでした。巨岩やハシゴが現れ、汗をかきながら開聞岳山頂に到着です。

9合目付近からの眺め
下りでしっかりと展望を楽しみつつ、森の中へ。南国特有の植物もしっかり愛でつつ行きましょう。

ツワブキ

ツチトリモチ

シロバナセンダングサ
下山して開聞岳の雄姿を西側から。締めくくりにふさわしい「薩摩富士」の雄姿です。

午後の開聞岳
バスにて薩摩半島の錦江湾岸を北上し、鹿児島市内の桜島フェリーターミナルへ。船上から鹿児島市街を振り返ると見事な夕日でした。

船上から鹿児島市街の夕日

フェリーから桜島
15分で桜島に到着です。登山はこれにて終了、お疲れ様でございました。
7日目
桜島の半日観光。ビジターセンターを訪れ、桜島の歴史と人々の暮らしを学びます。

歩いて体感します

溶岩の残る遊歩道
溶岩なぎさ遊歩道を歩いて周囲の溶岩を実際にご覧いただき、最後は南岳の麓、有村溶岩展望所へ。一面に広がる溶岩の上に根を張るクロマツの森の広がりが、時代による成長度合いで違うのが良く分かります。
またここから見る桜島は、見慣れた横長の桜島とは違い、円錐型を成しています。2つの山が並ぶ複合火山・桜島は、見る場所によって全くその姿が変わることが実感できます。

南側から見る桜島。麓の森の成長具合で噴火の時代が分かります

この日の噴煙は幾分穏やかでした
以上、「火山国」九州が生み出す山岳エリアのご紹介でした。本州よりも少しだけ早く進む季節では春のシャクナゲ、アケボノツツジから初夏のミヤマキリシマなどその時期のその地の花が可憐に出迎えてくれます。楽しく歩いて山を眺めて、そして温泉と九州郷土料理を楽しみましょう。
8日間の縦断ツアー以外にも様々な日数のツアーがございます。
2021花の登山シーズンのスタートはぜひ九州から!