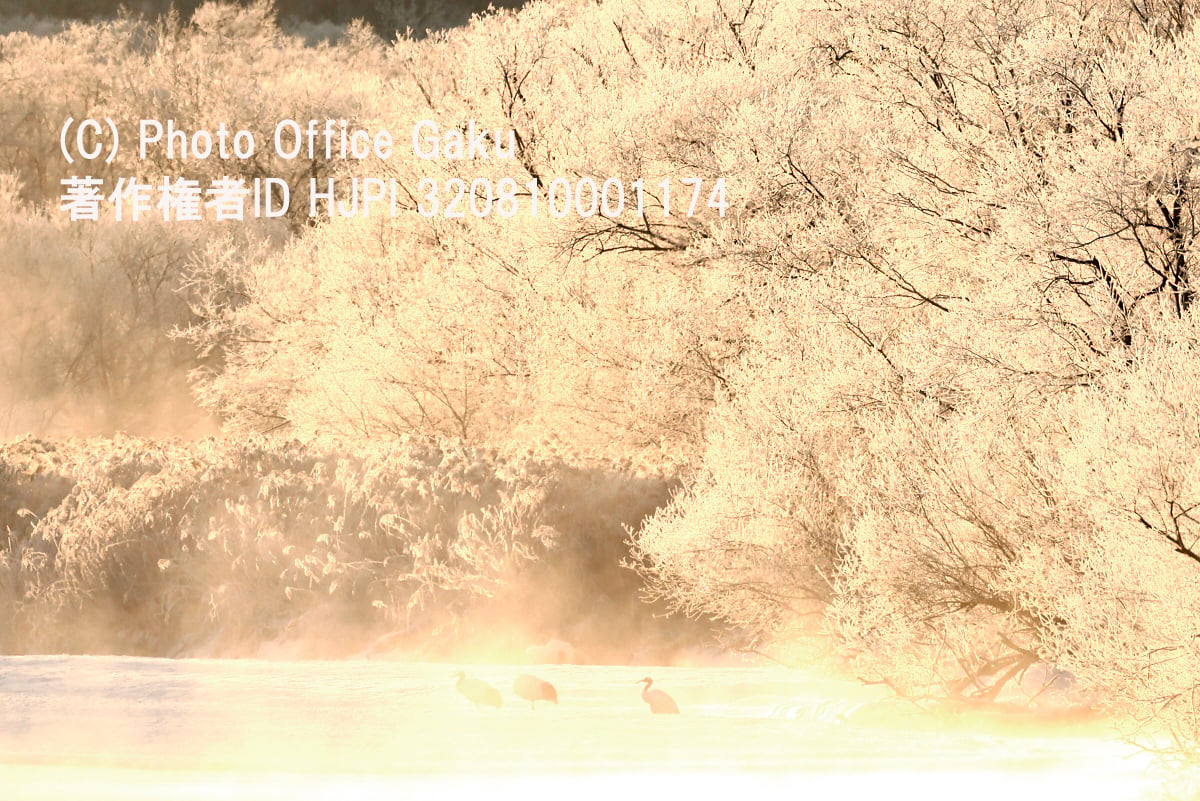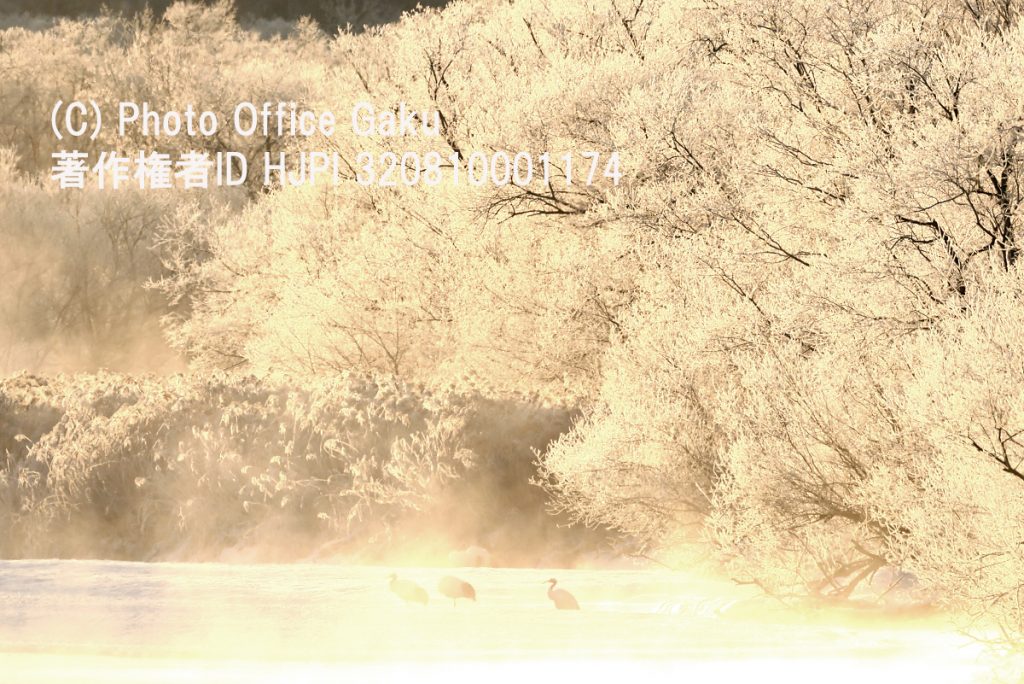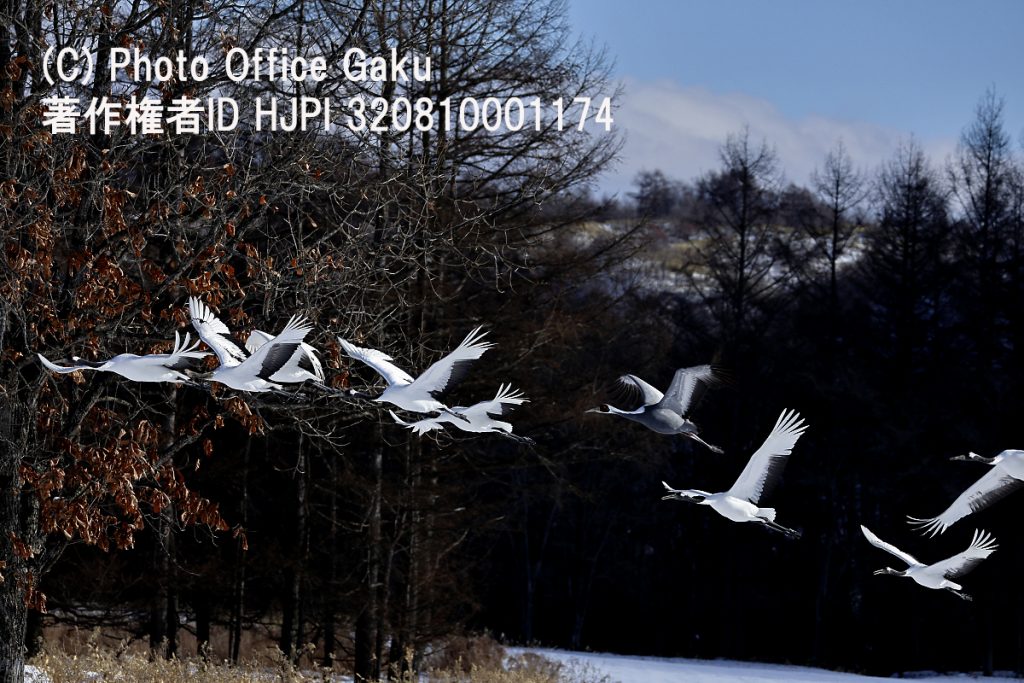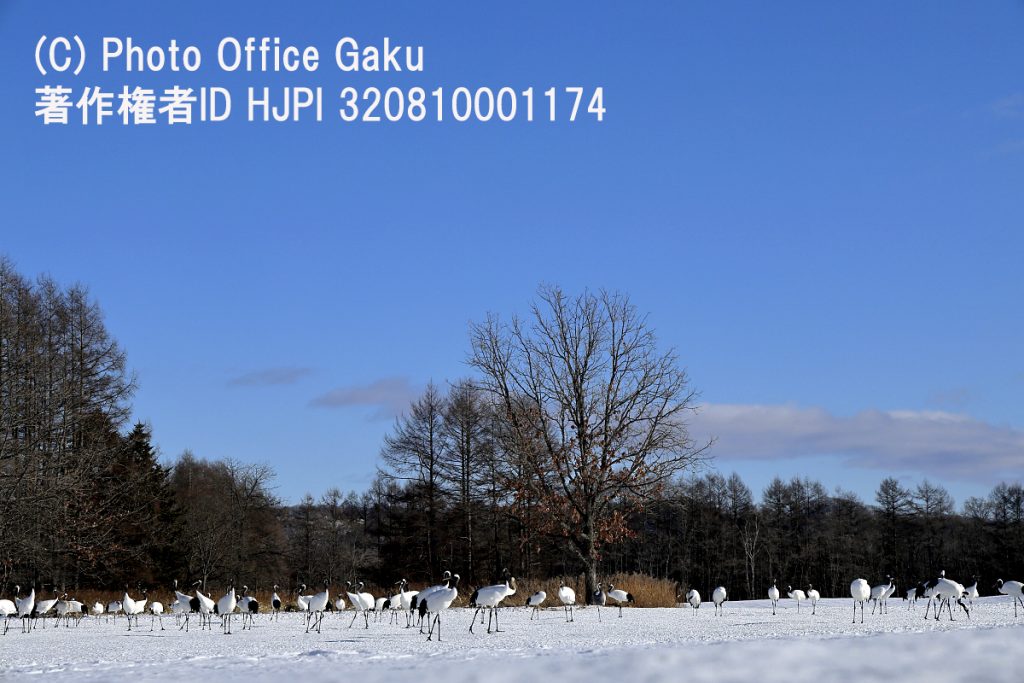ヒシクイ Bean goose ,
GJMG18 ,
チュウヒ Eastern Marsh Harrier ,
伊豆沼 ,
マガン Greater white-fronted goose ,
蕪栗沼 ,
カリガネ Lesser white-fronted goose ,
シマエナガ Long-tailed tit ,
コクガン Brant ,
オオハクチョウ Whooper swan ,
オジロワシ White-tailed eagle ,
オオヒシクイ Middendorf’s Bean Goose ,
ハクガン Snow goose
1日目
この時期としては気温が高く、時折雨の降る中でのスタートとなりました。
ガン類のねぐら入りを観察する前に、まずはシジュウカラガンを探すことにしました。マガンの群れをいくつか確認していくと、早速100羽を超すシジュウカラガンの群れを発見。周辺にもいくつかシジュウカラガンの群れが見られ、合計200羽ほどがいるようでした。二番穂の伸びた田んぼで、どの個体も必死に採餌していました。今期は暖かく積雪もほとんどないため、既にシジュウカラガンの大きな群れは渡去しています。今回見られたシジュウカラガンも間もなく開始する渡りに向けて、栄養を蓄えているのでしょう。
その後はガン類のねぐら入りを観察するために蕪栗沼へ。駐車場についてヨシ原を見ると、ハイイロチュウヒの雄と雌が飛んでいました。まだねぐら入りには少し早いためか、このハイイロチュウヒはその後も何度か飛んでくれました。曇天でやや暗かったものの、雄の青灰色の姿はとても綺麗でした。観察ポイントに着いて沼を見ると、前週に続きヘラサギとクロツラヘラサギが見られました。沼の近くの田んぼには、ねぐら入りを待つマガンの群れもあちらこちらに降りていました。16時45分を過ぎると次第にマガンの群れが沼へと戻り始め、日没後の17時15頃にピークを迎えました。無数のマガンが鳴きながら次々と沼へと戻っていく光景はとても壮観でした。
2日目
夜明け前にホテルを出発し、ガン類のねぐら立ちを観察するために蕪栗沼へ向かいました。観察ポイントに着くとちょうどマガンの群れが飛び立っていて、慌てて観察を開始しました。この日は天候も回復し、朝焼けの中での飛び立ちを見ることができました。
飛び立つガン類はほとんどがマガンでしたが、時折ヒシクイが混じり、シジュウカラガン30羽ほどの群れも見ることができました。マガンに続いてオオハクチョウも次々と飛び立ち、とても賑やかな光景となりました。
 餌場へと向かうマガン
餌場へと向かうマガン
マガンの飛び立ちが落ち着いてきた頃、沼で休んでいたオナガガモの群れが一斉に飛び立ちました。周囲を確認してみるとオジロワシが飛んでおり、どうやらこのオジロワシに驚いて飛び立ったようです。このオジロワシは沼の近くの木に止まってくれたので、じっくりと観察することができました。
 オジロワシ
オジロワシ
朝食後はカリガネのいるエリアへ。マガンはいつもよりも多く見られましたが、なかなかカリガネが見つかりません。そこで少し離れた田んぼも周ってみると、ようやくマガンに混じるカリガネを見ることができました。
 4羽のカリガネとマガン(左から4羽目)
4羽のカリガネとマガン(左から4羽目)
続いてはハクガンを探すことに。だいぶ苦戦しましたが、2時間近く探したところ、ようやく8羽のハクガンを見つけました。マガンとオオハクチョウに混じって採餌していましたが、少しして飛び立ち、丘陵を越えていきました。
 マガンとオオハクチョウに混じるハクガン
マガンとオオハクチョウに混じるハクガン
この日はヒシクイの群れも田んぼに降りていて、比較的近い距離で観察することができました。そのほとんどは亜種オオヒシクイでしたが、亜種ヒシクイも混じっており、体格や嘴の形状など両亜種の違いを見ることができました。
 亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイ(右から2羽目の顔だけ見えている個体)
亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイ(右から2羽目の顔だけ見えている個体)
この日の最後は蕪栗沼へ。沼にはオオハクチョウやヒシクイ、オナガガモ、ヨシ原ではベニマシコやオオジュリン、シジュウカラ、そして低空を飛ぶチュウヒも見られました。
 チュウヒ
チュウヒ
3日目
当初の予定ではチャーター船で仙台湾へ行く予定でしたが、強い冬型の気圧配置に見舞われ、朝から強い西風と高波となってしまい中止となりました。そこで、南三陸町の志津川湾へコクガンを見に行くことにしました。志津川湾はコクガンの餌となる海草のアマモが豊富なため、毎年たくさんのコクガンが越冬しています。
ポイントに到着すると、アマモを食べる30羽ほどのコクガンがすぐに見つかりました。また、オオバンが食べるアマモのおこぼれをいただく労働寄生という行動も見ることができました。強風のため海上の鳥のチェックはままならない状況でしたが、クロガモやハジロカイツブリなどが見られました。
 コクガン
コクガン
翌日も強風によりチャーター船の出港は難しそうであったため、午後は少しでも多くの海鳥を見るために仙台湾の海岸へ。堤防から沖合を見ると、ビロードキンクロやハジロカイツブリ、アカエリカイツブリが比較的近い位置に浮いていました。望遠鏡を使ってさらに沖を見ると、アビやミミカイツブリなども見られましたが、残念ながらウミスズメ類は見つけることができませんでした。
最後に漁港に立ち寄ると、魚の追い込み漁を行うたくさんのカワウと、ハジロカイツブリ、ホオジロガモなどが見られました。ホテルに戻った後、念のため船長に翌日の海の状況を聞いてみましたが、残念ながら翌日もチャーター船による観察は中止となりました。
4日目
相変わらず西寄りの強風によりチャーター船は欠航となったため、再び県北へガン類を見に行くことにしました。前日までとは一転、前夜からの積雪でガン類の採餌場は雪に覆われていました。雪田では餌が採れないため、マガンの群れもかなり少なくなっていましたが、何とか5羽のシジュウカラガンを見つけました。このシジュウカラガンも寝てばかりで、雪が融けるのを待っているようです。その後はマガンの群れがほとんど見つからないため、伊豆沼の湖岸に飛来しているシマエナガを見に行くことにしました。シマエナガは北海道で見られる亜種ですが、なぜか数年前から宮城県で毎冬見られています。今期は10羽以上の群れになっているようで、この日もポイントに着くとすぐに8羽ほどのシマエナガを見ることができました。また、シマエナガの群れと一緒にヤマガラやシジュウカラ、コゲラ、ベニマシコ、オオジュリンなども見ることができました。
駐車場でエナガの声を聞きながら今回のツアーは終了となりました。
4日間、大変お疲れさまでした。
 シマエナガ
シマエナガ
この記事を書いた人
田野井博之 たのい ひろゆき
1985年生まれ。小学生の時に野鳥の観察を始める。東北地方を中心に鳥類調査に携わりつつ、関心のある海鳥やシギ・チドリ類、チュウヒなどを見るため全国各地へ。特に海鳥の識別や生態に強い興味を持ち、国内外を問わず観察を続けている。




































とマナヅル 撮影・上山.jpg)